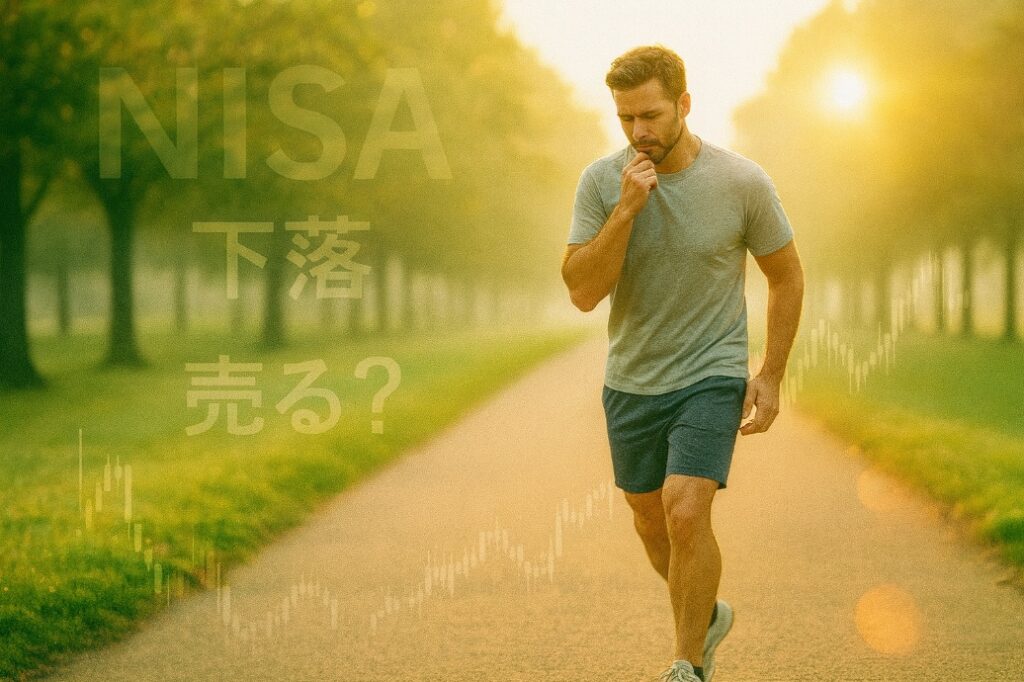
買った直後から評価額がマイナス。
数か月積み立ててもプラスに戻らない。
——そんな画面を見ると、不安や後悔、焦りが一気に押し寄せますよね。
「このまま続けて大丈夫?」「売ったほうがいい?」と迷うのは自然な反応です。
本記事は、そのモヤモヤを“判断できる材料”に変えるための道しるべ。
何が原因でマイナスなのかをいったん整理し、NISA特有の注意点を押さえたうえで、続ける/止める/売るの行動指針を具体的に提示します。
✅ 短期のマイナスは“異常”ではない。まずは「相場」「商品」「為替」のどれが主因かを分解する。
✅ NISAは損益通算不可。マイナスで売っても他口座の利益と相殺できない(=税務面の“取り返し”が効きにくい)。だからこそ軽率な損切りは避けたい。
✅ 売却しても“年間投資枠”は増えない。再利用できるのは非課税保有限度額(簿価ベース)で、翌年以降に使える。年の途中で“すぐ満額復活”はしない。
✅ 広く分散×低コストのインデックス積立なら、原則は継続+金額微調整でOK。商品設計がリスク過多(高コスト/テーマ過度/レバ)なら“将来分”の乗り換えを優先。
✅ 生活防衛資金>積立額。不安で眠れない水準は見直し対象。止めるよりも「一時減額・一時停止→計画再開」の順で考える。
✅ 最短フローで迷いを削る:「原因特定→NISAの制約確認→チェックリスト→行動(継続/減額/見直し/売却)」。
それでは早速始めましょう
目次
まず“なぜマイナスか”を分解する
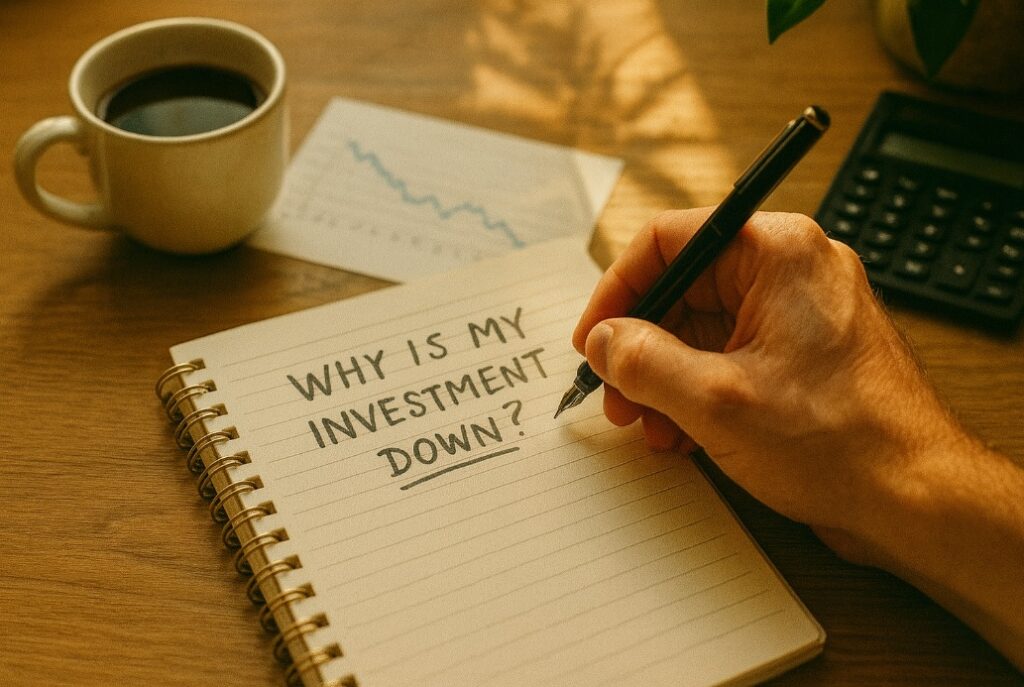
「マイナス」は一言でも、原因は複数が絡むのが普通。
相場・商品・為替の3視点で切り分けると、打ち手も見えます。
相場要因:
株式や債券が下落基調。金利上昇や景気見通し後退など、市場全体の波で起きる。
インデックス中心なら多くはここが主因。
商品要因:
- コストが高い(信託報酬・実質コスト)。
- 分散が狭い(テーマ型・特定セクター集中・個別株集中)。
- レバレッジやボラ高の商品を積立で保有——価格変動が大きく、含み損を抱えやすい。
為替要因:
外貨建て資産は円高で円評価が下がる/円安で上がる。
ヘッジの有無と自分の方針が一致しているか確認。
→ 原因の主因が分かれば、「継続が合理的か/見直しが先か」の判断が一段ラクになります。
NISA特有の“落とし穴”を把握

「NISAなら何でもお得」は誤解。
制度の制約を知らない損は避けたいところです。
- 損益通算・繰越控除は不可
NISA口座内の売却損はなかったものとみなされるため、特定・一般口座の利益と相殺できません。赤字で売っても税務面で取り返せない点は、売却判断に直結します。 - 売っても“年間投資枠”は増えない
新NISAには年間投資枠(最大360万円)と非課税保有限度額(最大1,800万円)があり、売却で再利用できるのは取得価額ベースの非課税保有限度額。しかも翌年以降に再利用する仕組みで、その年の年間投資枠が上乗せされるわけではありません。
つまり、「マイナスだけど一度売って、すぐに枠を使い直す」は思い通りにいかない可能性が高い、ということです。
「続ける/止める/売る」を決める5つのチェック

ここからは、意思決定のフローを最短で。
以下の5項目のうち、3つ以上が“YES”なら原則継続(不安が強ければ減額)。
NOが多いなら「商品見直し」へ。
- 分散の広いインデックス(全世界・先進国・広域)を中心に、つみたて投資枠で積立している
- 投資期間は10年以上を想定し、生活防衛資金は確保済み
- 信託報酬は低コスト帯(目安:年0.1%台〜)
- テーマ集中/レバレッジ/過度な個別偏重にはなっていない
- 為替ヘッジの有無が自分の方針と一致している
YESが3つ以上=原則継続。金額は「あなたが安眠できる額」に調整。
NOが3つ以上=商品見直し。ただしNISAの制約上、「今ある枠を売って買い直す」のは慎重に(後述)。
ケース別の実践アクション

「分かったけど、結局どう動けば?」に答える具体策です。
1) 低コスト・広く分散のインデックス積立が主軸なら
原則は継続が合理的。
下落期は買付単価が下がる=将来の回復局面で効くという積立の基本メカニズムが働きます。
- ただし金額は心の余裕に合わせる。不安が強いと“底で解約”の失敗を招きやすい。
- 市況ニュースで商品をコロコロ変えない。“仕組み”は長期で効きます。
2) 高コスト・テーマ偏重・レバ商品の比率が高い
期待とリスクの釣り合いを再確認。
値動きが激しく、心理的に耐えにくいなら、将来の買付分から低コスト・広分散へ切り替えを検討。
- いま保有分を即売り→買い直しは、NISAでは税務面の救済が効かないうえ、年間投資枠は増えないため慎重に。段階的な“新規の方向転換”が現実的です。
3) 個別株・高配当の集中が大きい
セクター偏り・減配リスク・銘柄個別要因でブレやすいのが悩みどころ。
- ETFや広域インデックスで分散を足して全体リスクを下げる。
- 「高配当=安心」ではなく、キャッシュフローと事業の持続性を見る習慣を。
- 乗り換えは“将来分の配分変更”から始め、売却は方針が固まってから。
4) 為替でブレている気がする
円高・円安で評価が動くのは当たり前。為替ヘッジは短期のブレを抑える代わりに、コスト上昇や長期リターンの差が生まれることも。
- 自分が欲しいのは「円建ての安定」か「世界の成長をそのまま取りに行く」か。意思表示として“ヘッジ方針”をメモするだけで、以後の迷いは減ります。
止める前にやる“資金とメンタル”のメンテ

決断を間違えるのは、商品よりメンタルと資金計画のほうが原因になりがち。
止める前に、以下をテコ入れ。
- 積立の“一時減額・一時停止”を選択肢に。完全停止や解約よりリスクが小さい。
- 生活防衛資金の再確認(目安:生活費○か月分など)。ここが薄いと、相場の波に耐えづらい。
- ルールの言語化:「○%下落でも積立継続」「年1回だけ商品点検」「ニュースで売買しない」——“自分の取扱説明書”を作る。
- 定点観測日を決める(例:月末にだけ評価確認)。“見すぎ”は不安を増幅します。
まとめ

「NISAでマイナス。続ける?やめる?」という迷いは、原因の分解(相場/為替/商品)と制度の理解(損益通算不可・枠の再利用は翌年以降・年間投資枠は上乗せされない)で、整理できます。
広く分散・低コストの積立なら原則継続+金額微調整、リスク過多な設計なら“将来分”の配分を変えるのが王道。
売却はNISAの制約を踏まえて“最後に”検討しましょう。
今日の一歩:
①評価低下の主因(相場/為替/商品)を書き出す → ②上の5つのチェックに答える → ③「継続・減額・見直し・売却」のどれでいくか1行で宣言。
紙に書く。それだけで判断がブレにくくなります。
本記事の引用元
・金融庁「NISAを知る:NISA特設ウェブサイト」— 新NISAの枠構成(年間投資枠・非課税保有限度額)など制度の要点
・金融庁「NISAを利用する皆さまへ(2024年からのNISA)」— 売却後の非課税保有限度額の再利用は翌年以降/年間投資枠は上乗せされない等を図解
・日本証券業協会「2024年以降のNISAに関するQ&A」— NISA口座の損失は損益通算・繰越控除不可の確認
・国税庁「NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A」— 非課税口座の譲渡損失はなかったものとみなされる旨の原則