
数十年前、私も投資信託の価値がなぜ増えるのか、よく理解できませんでした。
基準価額、分配金、複利…用語は知っても「結局なぜ増えるの?」が腹落ちしない。
本記事は“投資信託の中身=企業の集まり”に視点を移し、企業が利益を生み、配当や内部留保を積み上げると、なぜ投資信託の価値が上がりやすくなるのかを、経済の本質から丁寧に解きほぐします。
テクニック論は脇に置き、増える理由のコアだけに絞ります。
✅ 投資信託が長期で増える一番の理由は、組入企業が利益を伸ばし、配当か内部留保で株主価値が増えるから
✅ 市場は利益成長(=株主価値の増加)を放置できない。利益が積み上がるほど、株価は理論価値へ収れんしていく
✅ 投資信託の基準価額は保有資産の価値合計(純資産や見込み利益)に連動する。純資産を押し上げる最大因子は企業の稼ぐ力
では始めましょう
目次
投資信託は「企業の集合体」。増える源泉は“稼ぐ力”

まず大前提。投資信託は株式や債券などの資産のバスケットです。
株式を対象とした投資信託なら“企業群の一部所有者”になるのと同じ。
企業が「売上−コスト=利益」を生み、それを配当として株主に払い、または内部留保として再投資(設備、人材、研究開発、M&A)すれば、企業の純資産(自己資本)や将来の利益創出力が積み上がります。
その結果、「株主価値が上がる=株価の理論的価値が上がる」ため、投資信託全体の価値(=基準価額の“元”になる「純資産+見込み利益」)も押し上げられていきます。
重要ポイント:投資信託の基準価額は保有資産の価値の写し鏡。つまり「中身の企業が稼ぐ」→「保有資産の価値が上がる」→「基準価額も上がる」
利益は「配当」か「内部留保」で株主に返る

企業が生んだ利益の行き先はおおむね2つ。
- 配当として株主に現金で還元
- 内部留保として企業内に蓄える(次の成長投資へ回り、将来の利益・純資産・企業価値を押し上げる)
各企業がどちらを選んでも株主価値の増分です。
内部留保は「今は現金で受け取らない配当」と見なせる側面があり、長期の複利的な価値形成に直結します。
あなたが投資信託を購入すれば、その投資信託の持ち分に応じて内部留保分を将来受け取る権利をもらえることになるのです。
市場は“良い資産が安い状態”を長く放置できない

「内部留保が増えて純資産が積み上がるのに、なぜ株価が上がらないことがあるの?」
短期的には、流動性やマーケットの感情で割安放置が起こります。
しかし、利益や配当の積み上がりが続けば、理論価格(割引現在価値)は押し上げられ、市場価格はやがて株価上昇という結果で本質的価値に近づきます。
なぜなら、価値に対して価格が低い状態が続くと、この状態を発見して投資する人は、莫大な利益をあげることができるので、長期的には市場は放置できないからです。
これをシンプルに表すのが配当割引モデル(Gordon成長モデル)です。
株価 ≈ 来期配当 ÷(要求収益率 − 永続成長率)
ここで「来期配当」や「成長率」を押し上げる根源が企業の利益成長であり、内部留保による再投資です。
トータルリターンの“分解”で腑に落とす
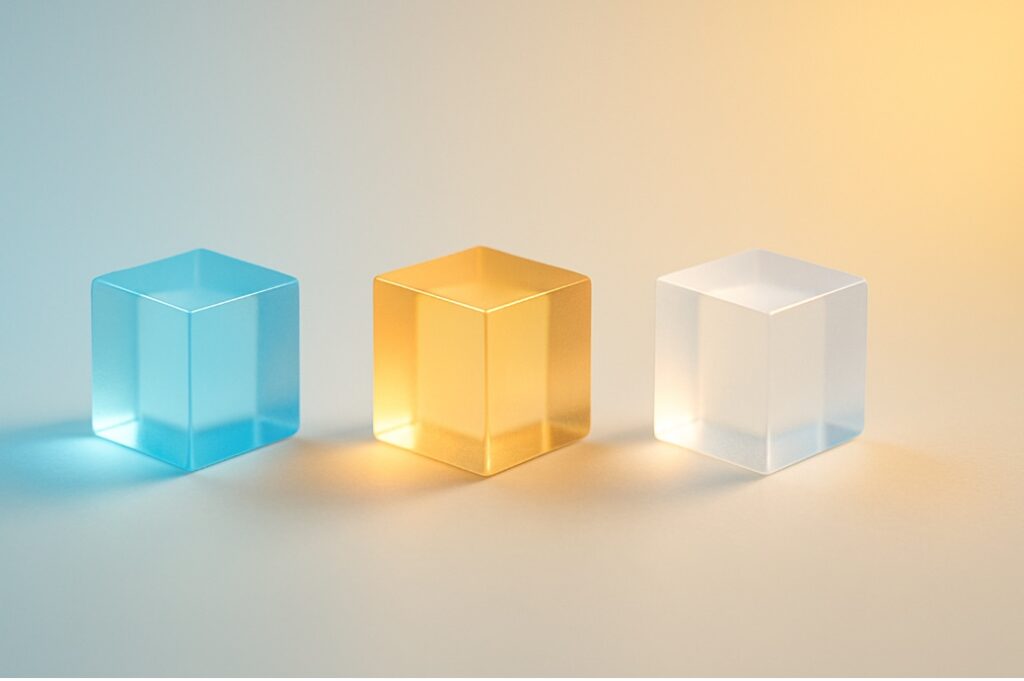
株式投資の長期リターンは、大まかにいうと、配当利回り+利益成長±評価倍率(P/E)の変化で説明できます。
- 配当利回り:企業が稼いだ現金の“いま”の還元
- 利益成長:内部留保と事業拡大が生む“将来”の還元
- 評価倍率の変化:人気・金利・期待が変わるとP/Eが伸縮(短中期のブレ)
長期では配当+利益成長の寄与が厚く、P/Eのブレは平均回帰しがちの傾向にあります。SSRN+1
だからこそ「中身の企業が稼ぐこと」に賭ける投資信託は、時間を味方にできるのです。
「分配金が多い=お得」の誤解をほどく
投資信託の分配は株の配当と似ています。
分配で現金が出れば、その分ファンドの資産(純資産)は減るため、基準価額は同額だけ下がる場面があります。
大事なのは、トータルリターン(基準価額の変化+分配)で評価することです。
企業が稼ぎ続ければ、分配で受け取るか、内部留保として企業内に残し将来に受け取るかの違いにすぎません。
分配金を再投資すれば、企業の稼ぐ力の積み上げが自分の資産成長に直結します。
注意:日本の投信には特別分配金(元本払戻金)があり、利益ではなく元本を返しているだけのケースもあります。非課税でも“得した”とは限らず、将来の増える力を細らせることに注意が必要です。
分配頻度が高いファンドが長期の資産形成に不利になりやすい理由は、主として以下の“摩擦”です(課税口座の場合は特に顕著)。
- 課税の早期化:分配のたびに課税が確定し、複利の足を引っ張る。
- 再投資の遅延:受け取ってから再投資するまでのタイムラグで機会損失が生じやすい。
- 取引コスト/スプレッド:売買の摩擦コストがトータルで積み上がる。
したがって、資産形成期は“再投資を前提”に、分配頻度の低い(または無分配の)ファンドが原則として合理的です。
一方で、取り崩し期(生活費の現金フローが必要なフェーズ)では、分配型を“計画的な取り崩しの手段”として使う選択もあり得ます。
重要なのは、頻度そのものを善悪で決めつけず、目的(形成か取り崩しか)に合わせることです。
目安:形成期は再投資型や年1〜2回決算の低頻度分配を基本線に。取り崩し期は必要額・税区分(NISA/課税)・再投資手間を加味して決めましょう。
よい投資信託の見極めチェックリスト

最短で“外しにくい”投信を選ぶために、迷ったらこの4点だけをチェックしましょう。
- コストの低さ:同じ市場を買うなら信託報酬は低いほど残りやすい(余計な摩擦を減らし、利益成長の果実を取り込みやすい) 金融庁
- 分配方針:積立期は再投資型が合理的なことが多い(トータルリターン重視) Investopedia
- 利益と資本効率:指数やファンドのEPS成長・ROE傾向を運用レポートで確認
- 還元姿勢:長期で配当性向や自己株買いを重視する市場・指数は、株主価値の積み上げが見えやすい
まとめ

投資信託が増える理由は、実は単純です。
中身の企業が利益を生み、その利益が配当や内部留保を通じて株主価値を増やし続けるから。
市場はその蓄積を無視できず、理論価値へと価格が収れんしていく──この企業経済のエンジンこそが、投資信託の長期成長につながります。
テクニックや目先の話題より、企業の稼ぐ力の積み上げに自分のお金を同乗させること。
これが“増える仕組み”です。
今日以降、あなたができる一歩は、稼ぐ企業の集合体を選び、余計なコストを避け、長期で持ち続ける設計に切り替えること。
投資において、時間は利益を重ねる企業の味方であり、あなたの味方です。
参考になれば嬉しく思います。
引用元リンク集
- 投資信託の基準価額=純資産÷総口数(一般社団法人 投資信託協会「投資信託の基礎知識」)。 投信協会
- Gordon成長モデル(配当割引モデル)の基礎(Investopedia/CFI)。 Investopedia+1
- リターン分解:配当+利益成長±バリュエーション(SSRN論文/MSCIの分解フレーム)。 SSRN+1
- 長期・積立の意義と手数料の基礎(金融庁NISAガイド等)。 金融庁
- 配当(分配)と価格の関係、トータルで捉える重要性(Investopedia)。 Investopedia